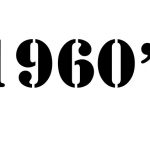読書週間とは?
毎年10月27日~11月9日までの2週間にわたり
読書の普及を目的として
講演会・展示会・お話し会・ポスターの作成など
読書に関連する行事を集中させた期間のこと
由来
もとになったのが1924年、日本図書館協会によって定められた
図書文化の普及、良書の推薦を目的とした「図書週間」です
その後「図書館週間」と名前を変え開催されていましたが
戦争の影響であえなく中止に
しかし、1945年の終戦から2年後の1947年に
「読書の力によって平和な文化国家をつくろう」と
図書館や出版業界、マスコミが一丸となり「読書週間」が開催されました
第1回はアメリカの「チルドレンズ・ブック・ウィーク」にちなみ
11月17日~11月23日に開催されました
各地で図書に関する展示会などが開かれると反響は大きく
次の年の第2回目からは文化の日を含んだ
10月27日~11月9日の2週間に延長され、現在まで続いています
時代を表す標語
読書週間では毎年事前に標語の募集をおこなっており
見事大賞に選ばれた標語は、その年のテーマに!
今年、第77回読書週間の標語は
「私のペースで しおりは進む」
記念すべき第1回目(1947年)の標語は
「楽しく読んで 明るく生きよう」
戦後らしい、前向きな思いが込められています
その後は読書に焦点を合わせた標語が続きます
「読書は人をつくる」(1955)
「よい社会 ひとりひとりの読書から」(1960)(1971)
「本との出会い ゆたかな時間」(1975)(1976)
「読書は新しい発見の旅」(1983)
90年代以降からは、おしゃれな印象の標語になっていきます
「風もページをめくる秋」(1991)
「落ち葉をしおりに 読書の秋」(2004)
「気がつけば、もう降りる駅。」(2010)
「おかえり、栞の場所で待ってるよ」(2019)
標語からその時代の背景や読書との関係性が表れていて
とても面白いですよね!
読書がもたらす効果
読書離れは現代の課題となっており
文化庁の平成30年度の調査によると
なんと47.3%が「1か月に1冊も本を読まない」との結果が!
しかし、読書にはさまざまな効果があることが分かっています
記憶力や集中力の向上
脳の中で情報を記憶し、整理しながら読み進める必要があり
情報を頻繁に記憶しながら進める読書は
記憶して思い出すという繰り返しを自然と行え脳の機能を強化します
ストレス解消
読書がストレス解消になる理由はいくつかありますが
「嫌なことから意識を逸らし没頭できる」と言う面が
大きいと言われています
研究によると6分の読書がストレスを68%も軽減する効果があり
音楽鑑賞や散歩、ゲームよりも効果的であることが証明されています
認知力低下の抑制
読書をしているとき「集中力」や「記憶力」など
認知機能の大部分が働き、それによって鍛えられ
認知機能低下の防止となり認知症の予防につながるといえます
読書をするという習慣はメリットがたくさん!
ぜひこの機会に、本を手に取ってみてはいかがですか?
関連記事

美味しいものが大好き、スタッフの岡田です。
休日はのんびり家で過ごすことが多くマイペースな性格です。
一生懸命、皆様の大切な方への贈り物をお手伝いさせていただきます!