「古希」とはどんなお祝い?古希の由来や風習を知って70歳の誕生日を素敵に演出しよう!
最終更新日:2023年3月27日

70歳の長寿祝いである「古希」。
いざお祝いするとなると、どんなお祝いをしたらいい?喜ばれる贈り物は何?テーマカラーは?と慌てて調べることになってしまう方も多いはず。
ここでは、70歳の誕生日に行うお祝いである「古希祝い」について言葉の由来や風習をご紹介します。
一生に一度のお祝いをする前に「古希」についての予備知識を身に着けておき、当日は素敵なお祝いを演出しましょう。
目 次
古希の由来、語源や意味は?
古希(こき)とは、70歳の長寿祝いです。
もともとは「古稀」と書き、長寿を祝う習慣が中国から伝えられた奈良時代には、初老といわれた40歳の祝いに始まる10年ごとの年寿祝いが行われていました。
これが、室町時代を通じて「還暦」(かんれき)「古希」(こき)「喜寿」(きじゅ)「米寿」(べいじゅ)の4つの長寿祝いとして定着していったのです。
77歳の喜寿、88歳の米寿と、年寿が10年周期ではなく文字を由来とするものへと変わっていったのに対し、古希は70歳の長寿祝いとして存続しました。
その理由は、古稀が中国唐代の詩人、杜甫(とほ)が詠んだ『曲江詩(きょっこう)』の中にある「酒債尋常行処有 人生七十古来稀」の一節に強い影響を受けているからだといわれています。
その意味は「酒代のつけなら私が行くところ至るところにある。しかし人生を70歳まで生きるのは非常に稀(まれ)なことだ」というものです。
この感慨は、長寿祝いが定着してくる室町時代の「人生50年」という感覚にぴったりでした。

江戸時代に入って世の中が安定すると、一般庶民の間でも学問や文芸への関心が高まり、杜甫の漢詩は教養として広まりました。
また平均寿命が徐々に延びたこともあり、古希を祝うという習慣は武士だけでなく一般にも馴染みのある風習として浸透していったのです。
世界に冠たる長寿国となった現代日本では、老年の実感が薄い「還暦」に対して、長寿を実感するのが「古希」であるともいわれています。
現実的に70歳は稀(まれ)ではなくなったことと、常用漢字に「稀」の字がないことから、現在では一般的には「古希」と記すことが多いです。
これと併せて、長寿祝いの意味も、70歳の長寿を迎えてもなお、「希望をもった人生を謳歌する」という未来志向のものへと変化しています。
おすすめページ
古希のお祝いは何歳でやる?
古希祝いは満年齢の69歳(数え70歳)で行うのがしきたりでしたが、最近では数え年のなじみが薄くなっていることから、満年齢70歳でお祝いする人が増えてきています。
満年齢と数え年
満年齢とは生まれた年を0年(0歳)とし、現時点までの時間を表したもので、最も一般的な年齢の数え方です。
これに対し数え年とは、生まれた時点の年齢を1歳とし、それ以後は元旦のたびに1歳を加算して歳を数える方法です。
2025年に古希を迎える方は、満年齢でお祝いする場合1955年(昭和30年) 、数え年では1956年(昭和31年)です。
古希の風習

古希のお祝いは、還暦と同様、ちゃんちゃんこや座布団などを揃えたり、家族が集まっての食事会などを開いたりするのが一般的です。
お祝いの基調色は還暦の「赤」に対して、皇族や皇帝、王などに許された高貴な色とされる「紫」を用います。
これは、伝統的な「古稀」の年齢への敬意を象徴するもので、古来最高位とし、気品と風格のある色として尊ばれた紫色の物を贈って祝う習慣が受け継がれています。
また、紫色には人を癒やす力も宿ると信じられているため、紫を配した普段身につけるものを贈ると良いとされています。
お祝いのしきたりは特にありませんが、赤ちゃんの産着から転じて還暦で身につけることが多い下着に対して、長寿者を敬う意味での上着などを贈ります。
由来が漢詩であるためか、「古稀」と地域の風土と結びついた風習はあまり見られないようです。
おすすめページ
また「古稀」が浸透した江戸時代は、敬老精神にあふれた時代だったといわれています。
武士には現在のような定年制度はなかったため古稀を過ぎても現役を務める人も多く、江戸後期には少なくとも50人が幕府の役職にあり、最高齢は94歳だったそうです。
女性の場合も奥女中に定年制度はなかったため、徳川家斉の時代には73歳で現役の奥女中の記録があります。
還暦まで勤め上げれば、老後の生活は幕府によって保障されていたそうですが、志を持って生涯現役を目指した方たちが、江戸時代にも大勢いたことには改めて驚かされます。
目上を敬う儒教精神の影響や、大家族型のライフスタイルであったことも大きいですが、江戸時代のこうした頼もしい高齢者の存在が、敬老精神を表す祝賀としての古稀を浸透させていったと考えられます。

健康寿命が延びた現代では、70歳で現役という方も増えています。
その意味では、「古希」のお祝いは長寿のお祝いに加えて、還暦に変わるセカンドライフの出発点という意味ももってきているようです。
古希祝いの祝い方で最も大切なのは、「長寿のお祝いをしてあげる」ということではなく、祝う側の敬老精神です。
古希を迎えた親や親せきという人生の先輩に学び、そのセカンドライフの門出を応援するお祝いにしましょう。
古希祝いを素敵に演出!人気のプレゼントは?

このように昔から人生の大きな節目となっている古希ですが、素敵なお祝いにするためにはプレゼント選びも大切なポイントです。
実際のお祝いにあたっては、どのようなプレゼントが人気なのでしょうか。
おすすめのプレゼントを3つご紹介いたします。
お花

どんなお祝いでも定番のプレゼントなのがフラワーギフトです。
古希のテーマカラーである紫色のフラワーアレンジメントで、お祝いを一層華やかにしてみませんか。
長く楽しんでもらいたいという場合は、生花より長持ちするソープフラワーやプリザーブドフラワー、ハーバリウムなどがおすすめです。
形に残る記念のプレゼントとして飾ってもらえます。
お孫さんの手作りプレゼント

お孫さんがいる方であれば、お孫さんの手作りのプレゼントなども喜ばれます。
似顔絵をフォトフレームに入れてプレゼントしたり、クッキーなど焼き菓子を手作りするのも良いでしょう。
特別感があり、より元気で長生きしてくれていることへの感謝の気持ちを表現することができます。
一緒に手紙などを添えると、あたたかな想いが伝わるでしょう。
旅行

予算や時間に少し余裕があるという方は、家族や親戚一同で旅行に行ってみるのも素敵です。
有名な温泉地や観光地であればアクティビティも充実しており、幅広い年齢層の方が楽しめることでしょう。
レストランやホテルでお祝い会を開催すると、思い出に残るイベントになります。
記念写真を撮ったり、ゆったりと豪華な食事を楽しんだり、非日常感を楽しんでみてはいかがでしょうか。
いつもと違うプレゼント「お誕生日新聞」がおすすめ!
「お誕生日新聞」とは、大切な方の生まれた日や二十歳の年、結婚式の日などの思い出の日の新聞を”大切な思い出”とともに贈ることができる、唯一無二のギフトショップ。
年齢性別問わず、ご家族の皆さまで楽しんでいただける商品となっており、オンラインだけでしか買うことのできない、大変めずらしいギフトショップです。
当時の紙面から伝わるおじいちゃん、おばあちゃんが生きてきた時代。
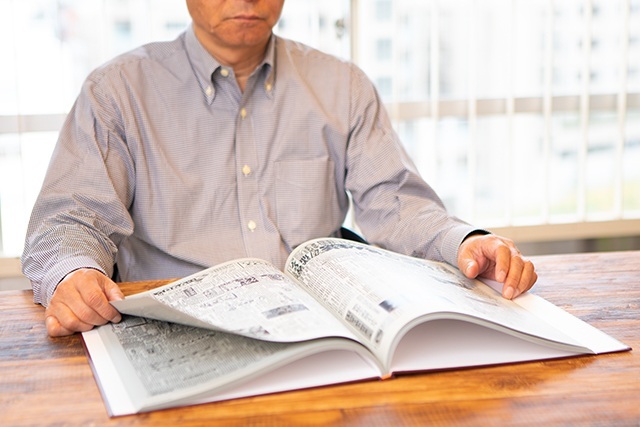
小さい頃の思い出、少年時代の思い出、二十歳の時の思い出、おばあちゃんと結婚した時の思い出などなど…
今までおじいちゃん、おばあちゃんから聞くことになかった当時の楽しいお話が聞けるかもしれません。
おじいちゃん、おばあちゃんが生きてきた時代をご家族皆さまで共有することで、家族のルーツや生まれた意味を知るきっかけにもなりますよ。
今まで長い間元気でいてくれたことに感謝を込めて、「お誕生日新聞」を贈ってみてはいかがでしょうか。












