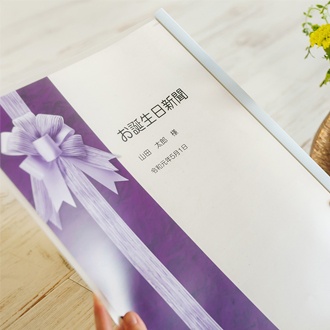喜びを分かち合う心「喜寿」の由来と風習
最終更新日:2023年3月27日
喜寿祝いのプレゼントなら「お誕生日新聞」
喜寿のお祝いに77年前の新聞を贈りませんか?
ありきたりなモノでは手に入らない特別な「思い出」を贈りましょう!
1万円以上のご注文で送料無料!
⇒喜寿祝いに77年前の新聞を贈る!人気商品総合ランキング
喜寿の由来

喜寿(きじゅ)は数え年の77歳で迎える長寿のお祝いです。
「喜」の草書体が「七十七」に見えることから77歳という長寿の喜びを祝う風習が生まれたのが由来とされています。
室町時代の終わり頃、平安後期の争乱から室町幕府の時代になって社会が安定してきたことで平均寿命が延び、中国から伝えられた「還暦」「古希」といった長寿を祝う風習が定着したことが背景にあります。
当時は、77歳も厄年のひとつとされており、77歳に喜の字をあてることで難を逃れる「喜の字の祝い(きのじのいわい)」とも呼ばれます。
また、喜寿は初めて日本で考案された長寿祝いです。100歳の「百寿」まで続く長寿のお祝いは、すべて文字の語呂合わせから生まれています。
他の長寿祝いと同様、喜寿のお祝いも、江戸時代に入ってから庶民にも広まり、江戸末期から明治にかけて活躍した国学者大国隆正が喜寿に際して詠んだ歌も残されています。
「ななぞちに七つあまれる喜びは/あらたなる御世にあへるなりけり」
明治4年に78歳で亡くなった大国隆正が、生きて明治維新後の新生日本を目の当たりにすることができた喜びを詠んだものですが、当時70歳の「古希」を過ぎてさらに喜寿まで生きるのは大変な喜びとされていたことが伝わってきます。
おすすめページ
喜寿のお祝いでは、紫色が基調色として用いられます。
この色は、満70歳の長寿のお祝いである古希と同じ色で、古くから高貴な色として尊ばれてきたものです。
紫色は、聖徳太子が定めた「冠位十二階(かんいじゅうにかい)」の最高位にあたる色で、平安時代以前は身分の高い人だけが身につけることが許される色として、厳しい禁忌が設けられていました。
こうした歴史から、日本では現在でも公式行事や叙勲など、紫色を特別な色として扱う習慣が残っています。
また、古代から潜在能力に作用する宗教色として尊ばれてきた紫色は、人の精神に作用し深い瞑想に導く色として尊重され、体の不調の際に紫色のものを身近に置くなどのしきたりもありました。
喜寿や古希の紫色には長寿への敬意と、健康の祈りが込められているのです。
喜寿の風習

喜寿の祝いは、暦の意味合いや儀礼として中国から伝わった「還暦」や「古希」にくらべると、日本で自然に発生した長寿祝いということもあり、日本の民間伝承と結びついた風習も多くあります。
そのひとつが室町時代の頃から使われた「火吹き竹」にまつわる風習です。
竈(かまど)や囲炉裏の火をおこすのに便利な火吹き竹は、毎朝欠かさず火をおこすために欠かせない道具でした。
火をおこす火吹き竹には、火の神につながるまじないの力があると信じられ、百日咳や耳垂れの病気祈願の際、年の数の火吹き竹を神仏に奉納する習慣が各地にありました。
かつては、喜寿の祝いに自然災害や火災除けのおまじないとして火吹き竹を配る風習も行われていました。
神奈川県の秦野(はだの)地方では、77歳の7月7日に火吹き竹を作り、火災除けのまじないとしたそうです。
また、栃木県では喜寿を「しちぼこ祝い」と呼び、火吹き竹を作って半紙に水引をかけて配るところもあるそうです。
他にも、信州の諏訪地方では、喜寿のお祝いに「羽織」「着物」「杖(つえ)」などを贈る習わしがあり、祝いを受ける家では紅白の餅に「喜」の字を記したものを配る風習があるそうです。
このように、喜寿のお祝いは、喜びを表す文字を由来としていることから、長寿のお祝いとともに、家族の安全や健康も祈願するお祝いとして民間伝承を取り込みながら伝えられてきました。
お祝いの時期は、古くは新年を迎えたお正月や誕生月に行われることも多かったようですが、特に決まりはありません。
現在では、ゴールデンウィークやお盆など家族が集まりやすい時期の他、敬老の日に合わせてお祝いすることも多くなっています。
厳密な作法や決まりごとはありませんから、祝われる方の意向に沿った食事会や贈り物をして楽しく過ごすといいでしょう。
おすすめページ
喜寿祝いのプレゼントなら「お誕生日新聞」
喜寿のお祝いに77年前の新聞を贈りませんか?
ありきたりなモノでは手に入らない特別な「思い出」を贈りましょう!
1万円以上のご注文で送料無料!
⇒喜寿祝いに77年前の新聞を贈る!人気商品総合ランキング