 今年、2023年4月1日から、出産育児一時金が42万円から50万円に引き上げられることになりました。
今年、2023年4月1日から、出産育児一時金が42万円から50万円に引き上げられることになりました。
出産は健康保険が適用されないので、基本的に全額自己負担となります。
実際どのくらいの費用がかかるのでしょうか?
■ 出産費用の全国平均
厚生労働省の発表によると、
令和3年度の出産費用の全国平均は 473,315円 です。
これは、比較的安いとされる「公的病院」の他、「私的病院」「診療所」を含めた全体の平均です。
■厚生労働省 令和4年10月13日「第155回 社会保障審議会医療保険部会」資料より
https://www.mhlw.go.jp/content/12401000/001000562.pdf
都道府県別で見た場合、「公的病院」のみのデータになりますが、一番高いのは東京都で565,092円。一番低いのは鳥取県で357,443円と、かなりの幅があります。
ちなみに、50万円を超える地域は、令和3年度では東京都、神奈川県、茨城県の3つでした。
こんなに違うのなら、里帰り出産した方がいいかしら・・・と考える人も多いかもしれませんね。
しかも、出産費用の平均473,315円には、一人部屋を選択した場合の室料差額や、文書料などの医療外の費用を含んでいません。
全部を含めると、病院に支払う妊婦さんの合計負担額は、6.5万円もアップして平均 538,263円 です。
そして病院代だけでなく、マタニティ用品やベビー用品の準備もありますし、他にもいろいろ必要になりますよね。
出産育児一時金50万円は、十分な金額とは言えないかもしれませんが、42万円から8万円も増えたことはかなりうれしいことですね。
■ その他にも利用できる制度
1 出産・子育て応援交付金
こちらは新しい制度で、自治体によっては2023年1月から始まっていますが、まだ準備段階の自治体も多いようです。
妊娠時に5万円相当、出産時に5万円相当のギフトが給付されます。給付のかたちはクーポンや現金など自治体によって違いますが、合計で10万円相当のギフトを受け取ることができます。
2022年4月1日以降に出産した方が対象となり、もう出産して子育て中という場合は、一括で10万円相当を受け取ることができます。
2 国民年金保険料の免除制度
対象になるのは第1号被保険者(自営業などの人)のみですが、出産日前後の4か月間(双子の場合は6か月間)国民年金保険料を免除してもらえます。こちらは追納の必要もなく、将来受け取る年金額にも影響しないので、ぜひ利用したい制度です。
このほかにも自治体によっては「出生祝金」が出たり、お住まいの地域によって異なる給付・助成がある場合があります。
上にあげた「国民年金保険料の免除」など、申請しないと適用されないものもあるので、対象になる場合は忘れずに手続きしてくださいね。
関連記事
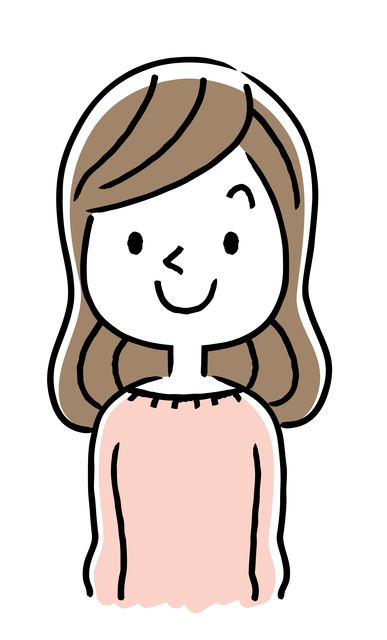
鳥が大好きなスタッフの長谷川です。外に出るとつい野鳥を探してしまいます。
いつも上の方を見てキョロキョロしている私ですが、仕事中はしっかり前を見て、みなさまに喜んでいただける商品をお届けできるよう頑張っています!








